2026年2月18日。
そのニュースは、単なる「クラブの募集終了」という経済的なトピックを超え、ひとつの時代の終焉として競馬界を駆け巡った。 ラフィアンターフマンクラブ、2026年7月をもって新規募集を終了。
【公式ホームページ:クラブ代表の声「ラフィアン最後の募集」】
「マイネル」の冠名。赤、緑袖赤一本輪の勝負服。
彼らは、常に競馬界の「アンチテーゼ」だった。 エリートが支配するクラシック戦線に、泥臭く鍛え上げられた雑草たちが殴り込みをかける。その姿に、我々はどれほどの夢を見せてもらっただろうか。
これは、約40年にわたり「常識」という巨大な壁に挑み続けた、岡田繁幸という稀代の相馬師と、その夢に賭けた会員たちの物語である。
第一章:反骨の相馬眼、北の地にて産声を上げる
時計の針を1986年に戻そう。
日本の競馬産業が、徐々に「社台グループ」の一強体制へと向かい始めていた時代。良血馬が高値で取引され、「高い馬=強い」という図式が絶対的な真理となりつつあった。
そこに、牙を剥いた男がいた。岡田繁幸である。
米国での修行で最先端の調教技術と栄養学を学び、帰国した彼が目にしたのは、血統書だけを信じて馬を選ぶ日本の古い慣習だった。
「走る馬は、値段じゃない。筋肉の質と、心肺機能だ」
彼が設立したラフィアンターフマンクラブのコンセプトは、当時の常識への挑戦状そのものだった。 募集価格は数百万円から一千万円台。父は決してリーディング上位ではない種牡馬たち。 しかし、岡田の相馬眼は、その馬体の奥に眠る「バネ」を見抜いていた。
「この馬は走るよ。見てごらん、このトモの送りを」 彼の情熱的な語り口(通称・岡田節)に魅了され、多くの競馬ファンが「一口馬主」という未知の世界に飛び込んだ。
彼らが共有していたのは、投資の利益だけではない。「俺たちの安い馬が、億越えの良血馬を負かす」という、痛快なジャイアントキリングの物語だったのだ。
第二章:「早期デビュー」という発明と、夏の風物詩
ラフィアンが競馬界に持ち込んだ最大の発明。それは「早期始動・早期デビュー」のシステムだ。
「馬は使い減りする」と信じられ、デビューを慎重に遅らせるのが美徳とされた時代に、ビッグレッドファームの坂路は真冬から湯気を立てていた。
徹底的に鍛え上げられたマイネル軍団は、6月の新馬戦開幕と同時に、他陣営を蹂躙した。 まだ仕上がっていない良血馬たちを尻目に、完成された肉体で逃げ切る。
「夏の福島・新潟はマイネルの庭」 「困ったときのマイネル頼み」
これには、岡田の「会員ファースト」の哲学が貫かれていた。
「会員さんには、少しでも早く配当を届けたい。そして、確実に勝ち上がらせたい」 だからこそ、早熟性を武器にし、賞金を稼ぎ、クラシックへの出走権をもぎ取る。
「マイネルは早熟で終わる」と揶揄されることもあったが、彼らはその批判さえも、勝利数という結果で黙らせてきたのだ。
第三章:1990年代、黄金のジャイアントキリング
その哲学が最初の頂点に達したのは、1996年の朝日杯3歳ステークス(現・朝日杯FS)だ。
勝ったのはマイネルマックス。 父ブライアンズタイム、母ササフラ。募集価格は決して高額ではなかったこの馬が、中山の坂を駆け上がり、G1のタイトルを奪取した。
岡田繁幸が、会員たちと抱き合って喜ぶ姿。それは「相馬眼ひとつで天下は取れる」ことを証明した瞬間だった。
そして1998年、スプリンターズステークス。 伝説の一戦が幕を開ける。
相手は、世界最強マイラーのタイキシャトルと、欧州G1馬シーキングザパール。日本競馬史上最強とも言われる「2強」が君臨していた。 誰もが3着争いだと信じていたそのレースで、大外から豪快に差し切った馬がいた。
マイネルラヴ
外国産馬全盛期に、ラフィアンが秘密兵器として米国から連れてきた刺客。 単勝オッズは2強に集中していたが、彼だけは違った。世界最強の2頭をねじ伏せ、G1馬となったのだ。 「マイネルが、世界を倒した」 中山競馬場を包んだあのどよめきと歓声は、ラフィアン会員にとって生涯忘れられない誇りとなった。
第四章:ステイゴールドの血と、長距離の覇者マイネルキッツ
2000年代に入ると、社台グループの壁はさらに厚く、高くなった。 サンデーサイレンス系良血馬の独占。
しかし、ラフィアンはここで新たな武器を手にする。「ステイゴールド」だ。
気性が激しく、小柄。エリートコースからは外れたこの種牡馬のポテンシャルを、岡田はいち早く見抜いていた。
その結晶が、2009年の天皇賞(春)。 主役はマイネルキッツだった。 重賞未勝利、前走の日経賞でも2着。12番人気という完全な伏兵扱い。 しかし、レースでは松岡正海騎手の強気の先行策から、淀の坂を利して抜け出した。 アルナスライン、ドリームジャーニーといった人気馬たちが猛追する中、最後まで衰えなかったその脚色。
かつて「早熟」の代名詞だったマイネル軍団から、3200mを制するステイヤーが誕生したのだ。 それは、ビッグレッドファームの過酷な坂路調教が作り上げた「折れない心」の勝利だった。 エリートたちが嫌がるようなタフな展開でこそ輝く。それが、熟成されたラフィアンの強さだった。
第五章:NHKマイルの涙、そして「総帥」との別れ
ラフィアンの馬たちは、時にドラマチックな奇跡を起こす。
2013年、NHKマイルカップ。 10番人気のマイネルホウオウが、直線のど真ん中を突き抜けた。 鞍上の柴田大知騎手は、デビューから苦労を重ね、一度は騎手を辞めようとした男。彼を拾い上げ、主戦として起用し続けたのが岡田繁幸だった。 ウイニングランで男泣きする柴田大知。 「総帥、やりました……!」 それは、馬だけでなく「人も育てる」という、ラフィアンというクラブの温かさが溢れ出した名シーンだった。
しかし、別れの時は唐突に訪れる。 2021年3月19日。岡田繁幸、急逝。 「ダービーを獲りたい」 その夢を追い続け、執念を燃やし続けた男の早すぎる死に、競馬界は喪失感に包まれた。
だが、物語は終わらない。 そのわずか2ヶ月後。5月の東京競馬場、オークス。 ゴールドシップ産駒のユーバーレーベンが、悲願のG1ゴールを駆け抜けた。 馬名はドイツ語で「生き残る」。
手塚調教師は空を見上げ、ミルコ・デムーロ騎手は涙を流した。 まるで天国の総帥が背中を押したかのような、完璧な勝利。 ミルコは「人生は難しい」と一言残して総帥への想いを語りました。
「岡田さんの愛したステイゴールドの血が、ゴールドシップの娘が、クラシックを勝ったぞ!」 それは、ラフィアンの歴史の中で最も美しく、最も切ない勝利だった。
第六章:2026年、決断の時。「馬を金融商品にはできない」
そして2026年。
ラフィアンターフマンクラブは、その歴史に自ら幕を引くことを決断した。
発表された理由は「金融商品取引法の規制」や「事務負担の増大」。 現代のコンプライアンス社会において、一口馬主は厳格な「投資商品」としての管理を求められる。
しかし、馬は生き物だ。 怪我もすれば、病気もする。スランプにも陥る。
「損をさせたくないから、補償を手厚くしたい」
「馬の状態に合わせて、臨機応変に、時には採算度外視で運用したい」
かつて岡田が実践してきた「義理と人情のクラブ運営」は、冷徹な法規制の枠組みの中では、維持することが困難になってしまったのだろう。
もし、ラフィアンがビジネスライクに徹し、会員を単なる「投資家」として扱えば、存続はできたかもしれない。
だが、彼らはそれを拒んだ。 「ラフィアンらしくあれないのなら、美しく散る」 その潔さこそが、最後までブレなかった岡田繁幸イズムの証明ではないか。
結び:最後の募集、最後の夢
ラフィアンターフマンクラブの新規募集は、2026年7月がラストとなる。 クラブ側は「過去最高のラインナップを揃える」と宣言した。
40年の集大成。 ビッグレッドファームの緑の屋根の下で、今まさに鍛えられている若駒たち。 彼らは知っているだろうか。自分たちが、「マイネル軍団」という偉大な歴史のアンカーであることを。
ラフィアンという名前が募集馬リストから消えても、ターフを走る赤と緑の勝負服がすぐに消えるわけではない。 最後の募集馬が引退するその日まで、我々の夢は続く。
かつて岡田繁幸が、目を輝かせて語ったように。 「この馬は走るよ。バネが違うんだ」 そんな声を空耳に聞きながら、我々は最後の世代を見守ろう。
ありがとう、ラフィアン。
ありがとう、マイネル軍団。
その反骨の魂は、永遠に競馬史と我々の心に刻まれるでしょう。
関連商品:【2025年JRA賞 馬事文化賞受賞作品】
相馬眼が見た夢 岡田繫幸がサンデーサイレンスに刃向かった日々
“マイネル軍団総帥” 岡田繁幸、反骨の71年。競走馬に狂う人たちの魂に届くノンフィクション。





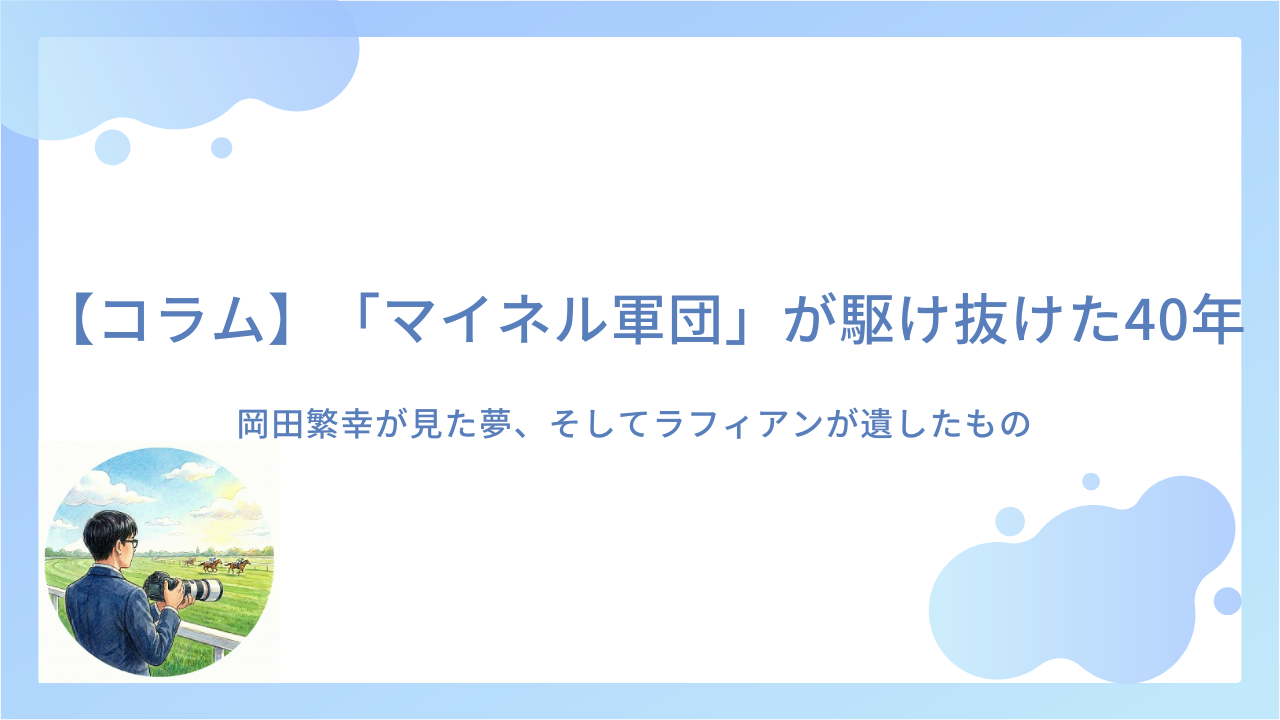


コメント